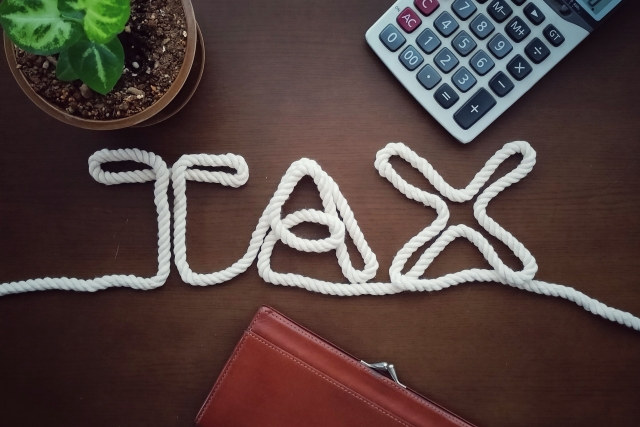
「税金ってなんのためにあるの?」そう思ったことはありませんか?
私たちが働いて得たお金や、買い物のときに払うお金の一部が「税金」として国に納められています。でも、この税金、いったい日本ではいつ、どうやって始まったのでしょうか?今回は、日本の税の始まりとその背景を、タイムスリップするようにたどってみたいと思います。
米が“お金”だった時代
今のように紙幣や硬貨がなかった昔、日本では「米」がとても大切な価値のあるものとされていました。人々の暮らしを支える主食でありながら、実は税金の代わりにもなっていたのです。
時代をさかのぼると、日本で本格的に税制度が始まったのは飛鳥時代(6〜8世紀)とされています。特に有名なのが、701年に制定された大宝律令(たいほうりつりょう)です。これは、日本で初めて本格的な法と制度を整えたもの。その中で、「租・庸・調(そ・よう・ちょう)」という3つの税の仕組みが定められました。
「租・庸・調」ってなに?
まず、「租」は農民が耕した田んぼから取れるお米の税です。お米の収穫の約3%を国に納めていました。いわば、「田んぼを使わせてもらってるから、成果の一部を返すよ」という形ですね。
次に「庸」は、労働の代わりに布や特産品を納める税です。国のために働くか、その代わりの物品を送る、という選択ができました。
最後に「調」は、地域ごとの特産物を納める税でした。たとえば、絹織物や陶器、漆器など。その土地ならではの価値あるものが国に集められ、地方と中央のつながりを強めていったのです。
なぜ税が必要だったのか?
ここで気になるのが、「なぜこんな仕組みができたのか」ということ。背景には、律令国家として中央集権を目指した朝廷の意志がありました。つまり、全国を一つのルールでまとめて、国としての力を強くするために、税の仕組みが欠かせなかったのです。
また、税を集めることで、都を守る兵士の給料、道路やお寺の建設、天皇の政治活動など、国を動かすための資源が確保されました。現代のように予算を組んで、国を運営するという発想は、実はこの時代から始まっていたのです。
課税の進化と、庶民の工夫
時代が進むにつれて、税の種類や形も変化していきました。平安時代には貴族が力を持ち、荘園という私有地が増え、税の免除を受ける領地も出てきました。鎌倉や室町の時代になると、**年貢(ねんぐ)**という形でお米を納める制度が広まりました。
ここで面白いのが、農民たちの工夫です。税が重くなると、実際の収穫量を少なく見せたり、作物を隠したりと、どうにか負担を減らそうとする知恵が生まれました。こうした“かけひき”も、税の歴史の一部なのです。
現代に続く「税」の意識
今の日本では、所得税、消費税、法人税などさまざまな税があります。形は違えど、「社会を維持するために、みんなが少しずつ負担をする」という考え方は、昔から変わっていません。
税は、「取られるもの」というイメージがあるかもしれませんが、実は自分たちの暮らしを守る仕組みでもあります。学校があり、病院があり、道路が整っているのも、税があるからこそです。
まとめ:税の始まりを知ると、今が見えてくる
日本の税の始まりは、田んぼで育てたお米を納めるところからスタートしました。それは、国を一つにまとめ、支えるための重要な仕組みでした。千年以上前の人たちも、「どうやって社会を成り立たせるか」を一生懸命考えていたのです。
私たちが今、毎日のように接している「税金」。それは単なるルールではなく、人々の暮らしの知恵と工夫、そして国家の成長の物語でもあるのです。でも、税金は安くあってほしいものですが…